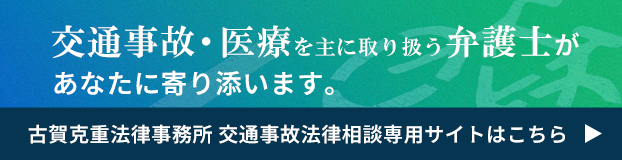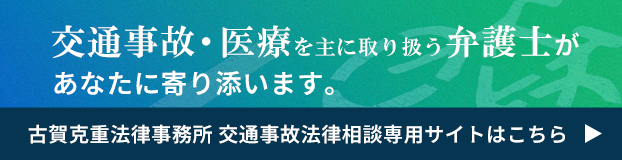さいたま地方裁判所 令和6年3月8日判決
自賠責9級16号顔面醜状等併合8級後遺障害を残す20代女子は瘢痕の存在が就労の機会や職種の選択を狭めてしまうことは否定し難い一方で時の経過により次第に緩和されていくと20%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した
解説
【事案の概要】
原告(20代女子)は、被告運転車両の後部座席に同乗中、被告車両が訴外車両に追突し、顔面多発骨折等の傷害を負い、約20日入院し約3年8ヶ月通院し、自賠責13級2号複視、同9級16号顔面醜状の併合8級認定の後遺障害を残して、既払金約870万円を控除し約6000万円を求めて訴えを提起しました。
裁判所は、原告の労働能力喪失率を20%と認定し、センサス女性学歴計平均の7割を基礎収入に67歳までの40年間につき後遺障害逸失利益を認め、原告のシートベルト不装着の過失を1割と認定しました(控訴後和解。自保ジャーナル2175号37頁)。
【裁判所の判断】
裁判所は、逸失利益については、原告は、その症状固定診断を受けた後、右眼眼球運動障害に伴う複視について自動車損害賠償保障法施行令別表第二13級2号に該当し、前額部右から上眼瞼の線状痕、オトガイ部の線状痕、右頸部の線状痕について同別表第二9級16号に該当し、これらの障害を併合して同別表第二併合8級の後遺障害等級認定を受けたことが認められ、特に原告の外貌醜状については、事故直後の状況と比較すれは相当程度回復したとはいえ、顔面の比較的目立つ位置に大きな瘢痕として残っており、原告が美容外科の自費診療により脂肪注入術を受けた後も、上記瘢痕はメイクにより完全には隠すことができない状態にあると指摘しました。
そして、原告が若年の女性であり、少なくとも一時期は容貌が重視される接客業に従事していたことも併せ考慮すれば、上記瘢痕の存在が原告の就労の機会や職種の選択を事実上狭めてしまうことは否定しがたい一方、上記瘢痕の程度は時の経過により次第に緩和されていくと考えられると判断しました。
そこで、就労可能年数の全期間を通算して20%の労働能力を喪失したものとして、原告の生活状況や基礎収入額の裏付け証拠が提出されなかったこと等から基礎収入を控えめに認定し(平成29年賃金センサス平均賃金・女性学歴計377万8200円の70%である264万4740円)、労働能力喪失期間40年間にて計算しました。
また過失相殺ついては、原告は、本件事故発生当時、被告車両の後部座席に同乗した際、シートベルトを装着していなかったため、本件事故により被告車両が前方の被害車両に追突した衝撃により、その顔面を前部座席に強打して顔面多発骨折等の負傷をするに至ったこと、なお、原告はその顔面以外には重篤な傷害を負わなかったことが認められ、一般に、同乗者にシートベルトを装着させることが運転者の義務である(道路交通法71条の3第2項本文)としても、シートベルトが装着者の生命、身体を保護する装備であって、その装着は容易であるのに対し、その不装着が交通事故発生時の損害の発生、拡大に大きく寄与する場合があることは自動車運転免許を保有していない者にも広く認識されているところであり、原告においてもこのことは十分理解していたと考えられるから、妊娠、疾病等、シートベルトの不装着につきやむを得ない理由があったとは認められない原告において、シートベルトの装着は可能かつ容易なことであったにもかかわらず、これを実行しなかったことにより自らの損害を発生、拡大させたことについては被害者の落ち度があるものとして、10%の過失相殺をするのが相当であると判断しました。
【ポイント】
9級16号外貌醜状を残す女子の後遺障害逸失利益が争われる事例は実務的に良くあります。裁判例としては赤本には以下の2つが紹介されています。
神戸地裁平成28年10月26日判決(自保ジャーナル1990号)は、9級16号外貌醜状を残すカウンセリング業務に従事する原告(30代兼業主婦)の後遺障害逸失利益計算につき、前額部の醜状痕は9級16号に相当すると認め、実収入を基礎収入に67歳までの29年間25%の労働能力喪失により認定しました。
名古屋地裁平成26年5月28日判決(交民47・3・693)は、空港ラウンジで接客業に従事する原告(30代女子契約社員)の化粧を施しても正面から見てそれと分かる右頬から右耳殻に至る長さ9cmの線状痕等(9級16号)につき、事故前実収入221万5520円を基礎に、34年間35%の労働能力喪失を認めました。
一方、東京地裁平成28年12月16日判決(自保ジャーナル1993号)は、自賠責9級16号認定の顔面醜状を残す原告(30代女子アルバイト)の後遺障害逸失利益につき、本件事故による逸失利益が具体的に発生したと認めることはできないと否認し、後遺障害慰謝料の加算事由として考慮すると830万円を認定しています。
等級や性別によって機械的に判断するのではなく、被害者の実情・職業への影響等から個別・具体的に判断する傾向がうかがわれます。