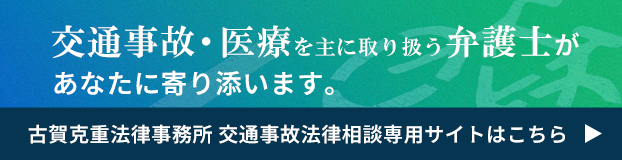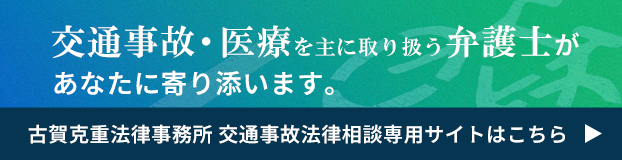名古屋地方裁判所岡崎支部 令和7年1月29日判決
路線バスに乗車し着席前に運転手がバスを発進させたため転倒を避けようと足を踏ん張って膝等を負傷したとする原告の供述等は客観的事実に整合しない部分があり信用性に疑問があるとして原告の受傷を否認した
解説
【事案の概要】
女性(50代)は、被告路線バスに乗車し、後方の座席に向かっていたところ、原告が着席する前に運転手がバスを発進させたため、原告が転倒を避けようと足を踏ん張ったことから、右内側・外側半月板損傷、両側膝関節挫傷、右外傷性変形性膝関節症等の傷害を負い、入院16日を含めて約9か月間通院したとして、約380万円を求めて訴えを提起しました。
裁判所は、原告主張の運転手の過失を否認し、本件事故による原告の受傷を否認して請求を棄却しました(確定。自保ジャーナル2192号128頁)。
【裁判所の判断】
運転手の過失の有無について、裁判所は、本件事故当時、原告はまだ着席しておらず、かつ、その動静に照らせば、着席しようとして空席に向かっている途中であることを否定し難い状況にあったものといえるとしました。
他方で、本件バスが発車する前に発車予告及び注意を促す自動アナウンスが流れていたこと、本件バスが発車した時点で原告が立っていた地点の周囲には、握り棒や座席肩の持ち手といった、原告が直ちに掴まって身体の支えとすることができる固定物が複数存在したこと(原告は、周囲に掴まれるものがなく、足で踏ん張って転倒しないようにするしかなかったと供述するが、本件バス車内の客観的状況に照らし、採用し難い)、本件バスの発車から原告が苦情を申し出るまでの前後方向の最大加速度は0.13Gに止まり、これはふんわりとしたアクセル操作と同程度のもので、停車中に車体の動揺によって生じる加速度と比べてもさほど大きな差はなく、バスの乗客が転倒するおそれがあるとされるレベルにも達していないことなどの事情に照らすと、原告の着席を待つことなく、実際に運転手が行ったような態様で発車したとしても、一般的にみて乗客の転倒や負傷を招くような危険性のある運転操作であるとは認め難いとしました。
また、本件発生時、着席しようとして移動中である可能性が否定できない乗客がいる場合、その乗客が着席するまでは路線バスは発車を差し控えなければならないという法令上の規定が存在した様子はなく、路線バス事業者の間において、そのような取扱いが一般化していたと認めるに足りる証拠もないとしました。
これらの事情のほか、公共交通機関たる路線バスには、時刻表に沿った定時運行をできる限り実現する責務が存在することも併せ考えると、本件事故時の状況の下において、原告が着席するまで本件バスの発車を差し控えなければならない注意義務を運転手が負っていたとは認められず、これを怠った点に過失があるという原告の主張は採用できないとしました。
本件事故により原告が受傷した事実の有無について、裁判所は、原告が本件事故により受傷したとする部位について、本件事故時に負傷したことを明示する医学的所見があるとは認められないとしました。
また、運転手による運転操作は、一般的にみて乗客の転倒や負傷を招来する危険性のあるものとは認め難い上、本件事故時の原告の挙動をみても、ふらついたりよろめいたりするなど、転倒のおそれを生じ、膝に大きな負荷が掛かるまで足を踏ん張らせる契機となる状況が生じていたようには見受けられないとしました。原告の陳述や供述をみても、本件バスが発車した際、身体を支えるために掴まれる箇所が付近になく、足を踏ん張ることで転倒を避けるしかなかったという説明は、本件事故時の客観的状況にそぐわないものであるし、そのほかにも、足を踏ん張った際の疼痛の有無やその後の疼痛の経過に関する説明が二転三転しているほか、本件事故から比較的近い時期にされた供述の中にも、本件バスが通常時と比較して急発車したとする点、原告以外にも2名程度の乗客が急発車により態勢を崩し、手すりに摑まることでようやく持ちこたえた様子だったとする点(本件事故時の車内録画映像によれば、立っていた乗客が2名確認できるが、発車時に態勢を崩した様子は見受けられないし、原告が苦情を申し立てるより前にそちらに視線を向けていた様子も確認できない)など、客観的事実に整合しない部分が見受けられるところであって、信用性に疑問があるとしました。
これらの事情に鑑みると、本件事故によって原告が膝等を負傷したとの事実について証明があったと認めることは困難であると判断しました。
【ポイント】
バスに乗車し着席前の発進による傷害等が争われた事例はいくつか見受けられ、例えば、神戸地裁令和4年2月16日判決(自保ジャーナル2122号)は、被告バスに乗車し着席する前に発進され手指等を座席に打ち付けて傷害を負ったとする原告につき、ドライブレコーダーの映像を見る限り、被告車の発進の対応は、急発進ではないし、原告がもんどり打つような動作をした状況も皆無である等から、原告の被告車乗車中に負傷した旨の供述は採用し難い等として、原告の受傷を否認しています。