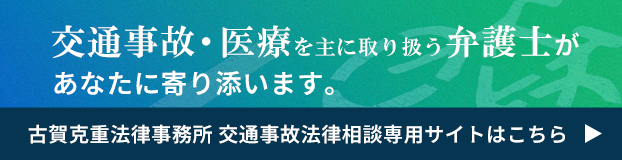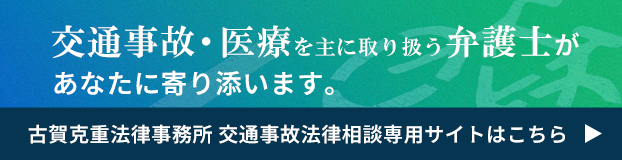千葉地方裁判所 令和6年5月13日判決
自賠責5級高次脳機能障害等併合4級後遺障害を残す40代兼業主婦の労働能力喪失率を就労実態等から45%と認定し、日常生活上の動作は自立しているから介護の必要性は乏しいと将来介護費を否認した
解説
【事案の概要】
40代兼業主婦の原告は、路上を自転車で走行中、被告運転の中型貨物車に追突され、左急性硬膜下血腫、脳挫傷、外傷性くも膜下出血、右橈骨遠位端骨折等の傷害を負い、約1年5カ月間治療し、自賠責5級2号高次脳機能障害、同12級8号右橈骨変形障害の併合4級認定の後遺障害を残し、既払金を控除した1億円強を求めて訴えを提起したものです。
千葉地方裁判所は、原告の労働能力喪失率を45%と認め、センサス女性学歴計全年齢平均を基礎収入に23年間につき後遺障害逸失利益を認定し、将来介護費は認められないと否認しました(確定。自保ジャーナル2176号1頁)。
【裁判所の判断】
裁判所は、逸失利益について、原告は兼業主婦であり、その給与収入は、平成30年には約204万円であったところ、平成31年は約29万円、令和2年は約17万円、令和3年は約84万円、令和4年は約93万円であったことが認められ、上記の減収が本件事故による傷害、後遺障害以外の事由によるものであることを認めるに足りる証拠はないと指摘しました。
そして、裁判所は、原告が令和2年7月、酒販店での仕事に復帰し、月曜日と木曜日の午前10時から午後1時までの時間帯で勤務を開始し、その後、令和3年1月頃からは、月曜日、火曜日及び木曜日の週3回勤務するようになり、同年春頃からはフォークリフトを利用した作業を行うようになった上、原告は、令和4年7月頃には、月曜日、火曜日及び木曜日の週3日、月曜日と木曜日はおおむね午前10時30分から午後5時30分(休憩1時間)、火曜日は午後1時から午後8時(休憩1時間)まで勤務するようになっていると認定しました。
以上をふまえて裁判所は、後遺障害により労働能力の92%が喪失されたとは認め難く、医学的意見書は「原告の労働状態とその内容から判断しても、本件外傷による高次脳障害に関する後遺障害等級は、第9級10号相当に留まるものと判断される。」としており、原告には高次脳機能障害以外に右橈骨遠位端骨折後の変形障害が認められることなどに鑑みると、財産的損害である逸失利益を算定するに当たっては、後遺障害による労働能力の喪失は45%程度と判断するのが相当であると認定しました。
また裁判所は、将来介護費について、医師が、原告について意思疎通能力、問題解決能力、社会行動能力については「困難はあるが概ね自力でできる」、持久力・持続力については「困難はあるが多少の援助があればできる」とし、高次脳機能障害の状態について特筆すべき事項として「社会的行動障害について、家庭での暴言が激しい。失礼な言葉を出すのががまんできない。」とし、さらに、食事、入浴、用便、更衣、外出及び買物について介護の必要はない旨を記載した「脳損傷又はせき髄損傷による障害の状態に関する意見書」を作成したことが認められることに加え、原告は、症状固定時にといて、食事、排泄、入浴等の生命維持のための日常生活上の動作は自立しており、金銭管理もでき、声かけ、見守りの必要性、相当性を基礎づけるに足りる事情も認められないことから、介護の必要性は乏しいとして、将来介護費は認められないと判断しました。
【ポイント】
被害者の就労や家事の実働状況などを丁寧に事実認定して、後遺障害逸失利益を認定して、将来介護費を否認した裁判例です。
5級2号高次脳機能障害の将来介護費が争われた事例として、以下のものがあります。
大阪地方裁判所令和3年2月4日判決(自保ジャーナル2094号)は、自賠責5級2号高次脳機能障害を残す40代男性の将来介護費につき、原告は父親と2人で生活し、入浴等の日常生活の動作は1人で行っており、公共交通機関を利用して1人で職業訓練校に行き来することもできることから、介護しての声掛けや看視が日常的に必要であるとまでは認められないと将来介護費を否認しました。
名古屋高等裁判所令和4年9月15日判決(自保ジャーナル2139号)は、5級2号高次脳機能障害を残す40代男性の将来介護費につき、今後妻の加齢により、一部職業介護の利用を余儀なくされる事態も予想されること等諸般の事情を総合的に考慮すると、将来介護費としては、平均余命を通じて日額3500円を認めるのが相当であるとして、平均余命の38年間につき日額3500円で認定しました。