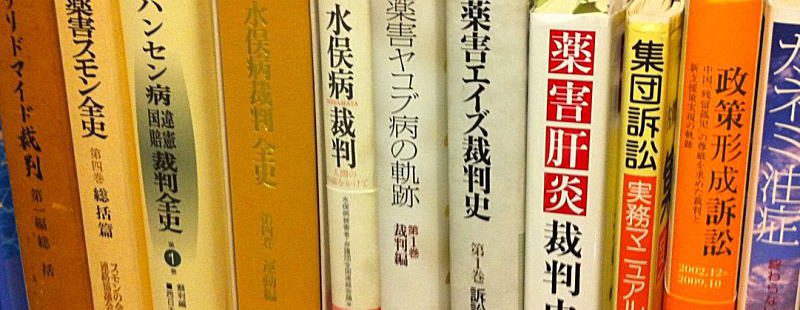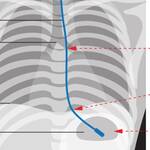薬害スモンから40年、難病対策を全面的見直しへ
国が難病対策の見直しを検討しています。
厚生労働省の難病対策委員会が提言をまとめたもの。「治療研究の推進」、「他制度との均衡と難病の特性への配慮」、「公平かつ公正な支援」、、「持続可能な仕組み」という4原則を掲げています。
日本の難病対策は薬害スモン事件を出発とします。
1955年(昭和30年)頃から下半身の痺れ、歩行障害、視力障害を訴える病気が発生。当初、「原因不明の奇病」と言われたその病気は、整腸剤として販売されていたキノホルムによる薬害、いわゆる薬害スモンであることが判明します。
厚生省は1969年(昭和44年)に研究班を立ち上げて、月1万円の医療費補助を開始。
そして、国は、1971年(昭和47年)10月、難病対策要綱を定めたのです。
難病対策要綱では、「調査研究の推進」、「医療施設の整備」、「医療費の自己負担の解消」という3原則がうたわれ、「福祉サービスの面にも配慮していくこととする」とされていました。
今回難病対策委員会がまとめた4原則と比較すると、「調査研究の推進」は同じですが、「自己負担の解消」という原則が、「他制度の均衡」「公平性」に変化していることが分かります。
つまり患者の経済的負担を増やす方向、助成をカットする方向でのバイアスも感じられます。
また難病対策として、厚生労働省が難病患者のデータベース作りに乗り出すことも検討されています。
しかし難病患者のデータベースは、マイナンバー制度と同様に、患者のプライバシー侵害につながらないような慎重な運用が求められます。そしてデータベース創設によって、最も恩恵を被るのは、政府が力を入れている「創薬」分野であることにも注意が必要です。
データベース作りは、同省が進める難病対策の一環。それぞれの病の患者がどこにどれだけいて、症状がどう変化しているのかを把握する。個人情報を保護しつつ、患者のデータを研究機関などへも提供し、薬の承認に必要な臨床試験をしやすくする。外国と共に臨床試験をする国際共同治験ができる環境も整える・・
・・難病対策の見直しでは、どの病に医療費を助成するかの基準を明確化する。現在、56疾患の患者約78万人に限られる助成対象を、300程度の疾患に拡大する方針だ。一定の負担を一部の患者に求めることも検討しており、医療費助成以外の支援策も検討していた(6月18日朝日新聞)
さらに、難病対策の検討に当たっての中間的な整理では、現在の難病対策の課題として、「医療費助成について、医師が患者のためを思い診断が甘くなる傾向があることが指摘されている」といった偏見に満ちた意見も平然と述べられています。
このように様々な思惑が交差する難病対策の見直し。
国は、各患者団体の意向を誠実にすくい上げるとともに、公平の名の下に、現在の難病患者に対する支援レベルをいたずらに引き下げないよう配慮する必要があるでしょう。
目次
投稿者プロフィール