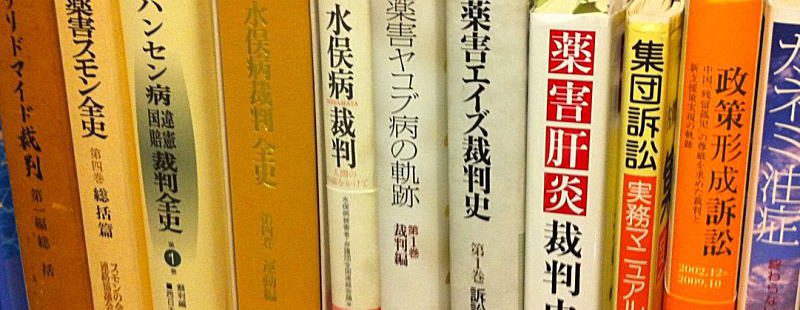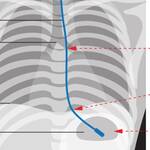「加藤一郎先生の人と業績」~集団訴訟の視点から
最新号のジュリスト(1380号)が、「加藤一郎先生の人と業績」という特集を組んでいます。
加藤一郎氏は東大教授として不法行為論などを研究するとともに、法務省の法制審議会の委員、民法部会長なども務めて、1983年に東大を定年退職した後は、母校の成城学園の理事長に就任するとともに、法律事務所を開設し、「様々な団体の役員、政府の委員を務められ、一時はその肩書きは130を越えた」(ジュリスト1380号11頁)そうです。
一方、集団訴訟を扱う弁護士にとっての「加藤一郎氏」というと、なんと言っても水俣病訴訟を巡っての「加藤・松野論争」を思い浮かべます。
ジュリストの特集号では一切触れられていませんので、若干長くなりますが触れてみたいと思います。
事の発端は、加藤氏が、判例タイムズ782号2頁(1992年6月20日)にのせた「司法と行政-水俣病をめぐって-」という論文でした。
当時、水俣病訴訟は、東京地裁、熊本地裁、福岡高裁、福岡地裁の順に相次いで和解勧告が出されてて、福岡高裁でも和解協議が開始された時期でした。しかし、福岡高裁における和解協議に国は加わらず、結局、東京地裁が平成4年2月判決を下し、国と熊本県の責任を否定するに至ります。
この東京地裁判決を特集した判例タイムズに、加藤氏は論文をのせます。
その論文の内容は、裁判所による和解の強要は不適切であるとした上で、国に和解勧告を強く勧めた裁判所を非難するといっていい内容でした。
水俣病訴訟で、裁判所が、和解に入ることを当事者、特に国に強く求めたことは、その点で、法的に司法の枠を越えたものであり、実質的に見ても、和解の見通しの立たないまま和解勧告をしたことについて、裁判官の見識が疑われるものであった。
そして、論文の最後を次のように締めくくり、司法消極主義を高らかに宣言しました。
要するに、司法、すなわち裁判官は、法による救済を与えるのが困難ならば請求を棄却するほかはないし、そうすればよいのである。あとの被害者救済が必要かどうか、必要だとすればどういう方策をとるかは、行政や立法の仕事だと割り切って考えるほかはない。
当時は、福岡高裁で和解協議中でしたから、高名な研究者のこの論文が、訴訟当事者にどのような思いで迎えられたかは想像に難くありません。
この論文の4か月後の判例タイムズ792号52頁(1992年10月15日)で、水俣病訴訟弁護団の松野信夫弁護士(現在、衆議院議員)が、「加藤論文は・・・そのまま容認できないような問題点も存すると思われるので、加藤論文に反論を加えつつあわせて判決と和解をめぐる司法の役割について触れてみたい」として、反論の論文を掲載しました。
加藤論文は、要するに水俣病訴訟などは裁判所で解決することはできないのであり、一応和解勧告するにしても、国が拒否した以上、さっさと和解を打ち切って判決をすれば良いし、全体的な解決はあとの行政や立法に任せておけば良いのである、ということのようである。司法はその限界をわきまえて、あとは高みの見物に徹せよとでも言うのであろうが、これは現場の裁判官の悩みや痛みをまったく考えていないと言わざるを得ない。
加藤論文はこの点、伝統的司法消極主義的な観点にとらわれすぎているようであり、しかもいくら加藤氏が法務省の顧問をしているとはいえ、これは国の代理人が書かれたのかと一瞬疑ったほど国の側に立って国の意図を見事に代弁している。加藤氏自身、・・・利益衡量論を標榜し、一方的な姿勢をとることを極力避けてきたと主張されておられることからすると、いささか不可解な感がぬぐえない
福岡高裁の裁判長として加藤氏の批判を受けた友納治夫氏も、その後、次のように反論しました(水俣病訴訟弁護団編『水俣病救済における司法の役割』(2006年、花伝社)95頁)。
福岡高裁での和解協議の進行中に、元東大総長の加藤一郎先生が・・水俣病訴訟のように広くかつ根深い事件を和解で解決するのは無理なのであり、国が拒否しているのに裁判所が和解に入ることを強くもとめたのは司法の枠を超えたもので、和解の強要は憲法の精神に反する、という趣旨の批判をされました。
水俣病訴訟が広く根深い大事件であることは私も同感ですが、だからといって、この事件を和解で解決しようと試みたことが間違っていたとは考えておりませんし、先ほど述べたような経緯から、裁判所が国に対して和解への参加を何度も呼び掛けたことが和解の強要で司法の枠を超えたものであったとは全く考えておりません。
また、元仙台高裁長官で大学教授の田尾桃二先生も、全国裁判所書記官協議会の総会で、・・この事件の和解の勧試も国への参加のすすめも悪いこととは思えないと語っておられます・・そういうようなことも励みになって、私共としては最後まで和解の協議を続けさせていただいた・・
その後、関西水俣病最高裁判決が、国の責任をそもそも認めたこと、司法改革が進み裁判所への期待がより高まっていること、薬害HIV、薬害やコブなど裁判所がイニシアチブをとって国を説得して和解を成立させる集団訴訟が相次いでいること等からして、加藤一郎氏の論文は、残念ながらその内容、発表した時期、そしてその後の司法の流れからしても、正鵠を得ていないものであったと評価せざるをえないでしょう。
目次
投稿者プロフィール