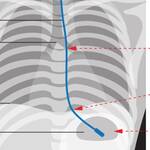超高齢者にかかわる終末期医療と医療過誤訴訟、福岡地裁医療関係訴訟運営改善協議会から見えてくるもの
目次
第17回医療関係訴訟運営改善協議会が福岡地方裁判所で開催
第17回の医療関係訴訟運営改善協議会が福岡地方裁判所で開催されましたので、患者側弁護士として出席してきました。
福岡地方裁判所が主催して、医療過誤訴訟の運営について各当事者が出席して意見交換して、制度改善につなげようという試み。
最高裁判所の声かけにより、全国の裁判所でも実施されています。
第17回の今回も多数の参加があり、裁判官・書記官、患者側弁護士・医療機関側の弁護士らに加えて、福岡県内の大学病院等から医師11名、法学者3名など約50名近くが参加しました。
裁判所から最近の福岡地方裁判所の医療過誤訴訟の現状について報告が行われ、続いて福岡県弁護士会から医療ADRの実情についても報告しました。
超高齢者にかかわる終末期医療をめぐって
東京地裁のように過去の具体的ケースを取り上げて、過失や因果関係について複数の専門医が意見を述べて、法曹家がさらに議論を深めて意見交換していくやり方もありますが、なかなか準備が大変です。
福岡地裁の今回の協議会は、特定のテーマを取り上げてそれぞれの立場から報告を行い、フランクに意見交換するスタイルが取られました。
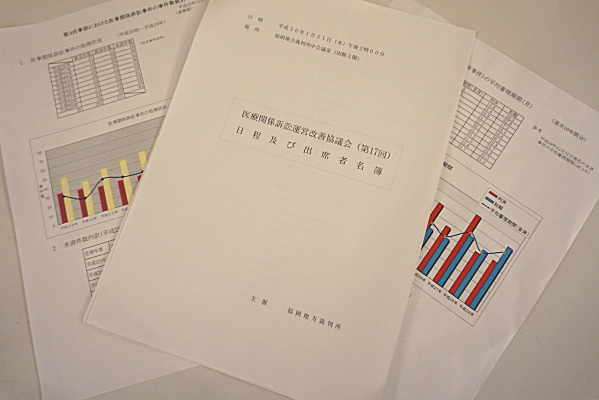
17回目の今年は「超高齢者にかかわる終末期医療」が取り上げられました。
まず久留米大学の新山修平准教授からスライドに基づいて報告がありました。
国連の世界保健機関(WHO)の定義では、65歳以上が前期高齢者、75歳以上が後期高齢者とされ、日本でも高齢者は65歳以上と定義されています。ですがこの定義には医学的・生物学的に明確な根拠はありません。
そこで日本老年学会・日本老年医学会は、「65歳から74歳」を准高齢者、「75歳から89歳」までを高齢者、そして「90歳以上」を超高齢者と定義づけることを提言しています。
内閣府の発表する平成29年度版高齢社会白書によると、高齢化率は2016年には27・3%、2060年には38・1%に達すると予測されています。
また厚労省の平成28年人口動態調査にれば、かつては9割だった在宅死が、2016年には13%に落ち込み、病院等の施設内での死亡が85%に達しました。
かかる状況を受けて厚労省が2007年5月に発表した「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」は、患者本人の意思決定を基本として、主治医の独断ではなく医師以外のスタッフも入ったチームで判断する、としました。
この終末期医療の決定プロセスは2018年3月に改訂予定になっています。
厚労省の改訂案は、原則は変えずに病院だけでなく介護施設や自宅でも活用しやすくすることを提言。
そして看護師や社会福祉士、介護支援専門員、介護福祉士らがチームに加わることを想定しています。
さらに希望に沿えるように、患者家族・医療者らが繰り返し話し合うべきだとしています。そしてその話し合いの内容は文書にまとめることも盛り込まれています。
新山准教授は欧米豪にみる高齢者の終末期医療を紹介し、高齢者の終末期には積極的な治療を行わない地域や医療機関を説明し、私見としては保険制度の違いもその一端の可能性があると指摘しました。
そして緩和ケアのシンポとともに、エンドオブライフ・ケア(EOLケア)への関心が高まっていると指摘。
EOLケアとは、死が避けることができないものとなり、予想される生命予後が限られたときに行われるケアを差し、最後の12か月を表現するものとされています(豪州緩和ケア協会)。
非がん疾患はがんに比べてEOLケアの話を切り出しにくいこと、そして日本の医師は治療上、「何かをする」トレーニングを積んでいても、「やらない」と選択する術を学んでいないため、つい「これ以上、治療しなくていいの?」と考えてしまうといいます。
まずは政府主導で議論を行っていき、国民的議論がなされて欲しいと締めくくりました。
高齢者に対する医療に関する裁判例の紹介
高齢者特有の医療事故としては、医療施設ないし介護施設における転倒・転落、誤嚥・異食、感染症・褥瘡、徘徊・無断外出、身体拘束、入浴事故などが良く問題になります。
最近の医療相談の傾向としても患者さんが高齢者のケースがかなり増えています。
福岡地方裁判所医療集中部の裁判官からは、そのような典型事故類型以外のケースにおける過失の判断において、高齢者であることを考慮した裁判例として3例が紹介されました。
一つは薬剤投与及び術後管理に関する事例である宮崎地方裁判所平成26年7月2日判決です。
全身麻酔下の腰椎椎弓切除術を受けた患者が低酸素性脳症を発症して植物状態に陥った事案について、裁判所は,医学的知見によれば,本件麻酔薬の作用遷延に起因する気道閉塞等によって低換気状態になって低酸素血症を起こし、低酸素性脳症を発症したと認められるとし、医療機関等に対して、合計約5600万円の支払を命じたものです。
裁判所は、
高齢者に対して鎮静薬、麻薬性鎮痛薬及び筋弛緩薬を併用した全身麻酔を行った場合には、その作用遷延により覚醒遅延や気道閉塞が起こる危険性が通常に比して高いため、注意深く意識状態や呼吸状態の確認を行い、覚醒遅延や気道閉塞等による低酸素血症が高度となるなどといった最悪の事態を避けることが必要とされていること、抜管後に患者を手術室から退室させる際には、SPO2を監視するためにパルスオキシメーターを装着し、また、病棟看護師に対して退室後に予測される患者の変化と継続が必要なケアについて申し送りをしなければならないとされていること、抜管後の呼吸確認は、単なる胸郭の動きのみで判断すると舌根沈下が判明しないことがあるため、呼気を感じる、聴診での呼吸音の確認など、複数の観察項目で行うとされていること等が認められる
と医学的知見を認定した上、患者が手術室から退出した際、医師は呼吸管理の教育を十分に受けていない看護師に対し、呼吸に注意するよう告げたのみで具体的な方法について何ら指示しなかったことや、必要に応じた措置等を行うよう申し送りをする等の注意義務を怠った過失があると認定しました。
もう一つは適応に関する事例である奈良地方裁判所平成19年7月19日判決です。
下肢閉塞性動脈硬化症等の高齢者の患者に対する治療で死亡した事案において、直接死因は急性心筋梗塞である可能性が高く、また、小脳出血が生じた原因は、患者の高血圧症によるものであるとして請求を棄却した事案です。
争点は色々ありますが、患者はVPシャント術の適応がないのに施行した過失を主張していました。
これに対しては、裁判所は患者が高齢者であることもふまえて以下のように判断しました。
患者は本件当時81歳であり、若年層に比べて脳が萎縮していたため、小脳出血後の頭蓋内圧の上昇は比較的軽度であったと考えられること、血腫除去手術は81歳の患者には負担が重いことなどから、保存的治療が第1選択であった。そして患者が安静を保てず起き上がるなどしていたことからうすると、脳室ドレナージではなく、VPシャント術を行ったことは妥当である
さらに延命措置に対する患者及びその家族の意思が問題となった東京地裁平成28年11月17日判決も紹介されました。
入院していた患者(当時89歳)に対する延命治療について、患者の相続人である妻らが延命治療を拒否したため、医師が延命治療を実施しなかったため、患者が死亡しました。
それに対して、相続人の一人である原告が、自分の意思も確認すべきであったのにこれを怠った過失があると主張したという事案です。
東京地裁は、
厚生労働省が平成19年5月に策定した「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」によれば、医師は、終末期医療の方針決定において、患者の意思が確認できる場合には患者の意思決定を基本とし、患者の意思が確認できない場合には家族から患者の推定される意思を聴き取り又は家族と十分に話し合うなどして、患者にとっての最善の治療方針を採ることを基本とすることとされている。本件ガイドラインは法規範性を有するものではないが、終末期医療の方針決定における医師の注意義務を検討する上では参考となるものであるから、以下では、本件ガイドラインの場合分けに沿って検討を進める
とした上で、まず患者の状態からすると患者自らは意思決定できる状態ではなかったと認定しました。
その上で、医師が患者の家族からの聞き取りや話し合いが十分であったかについて検討して、過失を否定して請求を棄却しました。
医師は、患者の終末期医療の方針決定において、被告Y2を患者の家族の中のキーパーソンであると認識し、被告Y2の意見を参考にした上で、患者について、経鼻酸素吸入は当直時間帯を除いて行わず、心停止に陥っても心肺蘇生は行わないことを決定しているところ、医師が患者の家族の全員に対して個別に連絡を取ることが困難な場合もあり、また、延命措置には費用や介護の分担など家族の間で話し合って決めるべき事柄も伴うことからすれば、上記のようにキーパーソンを通じて患者の家族の意見を集約するという方法が不合理であるとは認められず、そのような方法を採ることも医師の裁量の範囲内にあると解される。
なおこの裁判例は、「キーパーソン以外の家族がキーパーソンと異なる意見を持っており、そのことを医師において認識し得た場合には、その者からも個別に意見を聴くことが望ましい」としつつも、具体的な事案に照らして原告が医師らに対して何らかの具体的な意見を述べたことは認められないと事実認定しています。
終末期にいかに患者の権利を実現するか
この日の協議会では全ての報告が終了した後に、意見交換が行われました。
意見交換では東京地裁の裁判例に関連して、医療現場から、日本における終末期医療の難しさ、そして患者以外の家族との意思疎通の難しさについてコメントがありました。またいわゆる「キーパーソン」が誰か分からないことも出てくるという現場の悩みも出されました。
それに対して日本弁護士連合会における議論をふまえて、人生の最終段階における意思決定だから、患者のこれまでの人生観・価値観を分かる人がキーパーソンに自然になってくるはずだという指摘もありました。
終末期には患者自ら意思表明できなくなっているケースが少なくありません。
そこで患者が意思決定能力を失う前に、「事前指示」によって意思決定することが考えられたわけです。
カリフォルニア自然死法(1976年)を皮切りに世界各国で法制化が行われていますが、日本では定められていません。
結局は、患者・家族と医療機関が繰り返し意思疎通を図り、死に向かう患者の意思決定権をいかに実現するかに行きつくわけですが、患者がそもそも意思決定できない状態といえるのか、患者の意思が変遷している場合にどう考えるのか、家族の意見が分かれている場合はどうするのか・・・等、医療現場では様々な悩みも出てきます。
誰しもが必ず迎える「死」への自己決定権という重たい問題について、改めて考えさせられる医療関係訴訟運営改善協議会になりました。
投稿者プロフィール