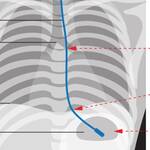最高裁裁判官から見た弁護活動のポイントとは、大橋正春元最高裁判事講演会
目次
大橋正春元最高裁判所裁判官の講演会が開催
元最高裁判事である大橋正春弁護士の講演会が10月20日、福岡県弁護士会にて開催されました。
大橋弁護士は1968年に司法試験に合格した後、1972年に第一東京弁護士会に登録(司法修習24期)。
1976年にハーバード・ロースクールを終了し、1983年から事務所を開設。2012年から2017年4月まで最高裁判所裁判官を務めました。
この日の講演会は、佐賀県弁護士会の稲津高大会長(47期)が、大橋弁護士の司法研修所教官時代の教え子だったことから実現したもの。福岡県弁護士会と九州弁護士連合会の共催となり、福岡以外の各単位会にもテレビ配信されたうえ、「最高裁判事から見た弁護活動のあり方」と題して4時間に渡る貴重な講演会が行われました。
印象に残る事件
大橋弁護士からは実際に最高裁で担当した複数の事件についても解説がありましたので、一部を紹介します。
最三小平成28年3月1日判決はメディアでも大きく取り上げられた事案です。
認知症にり患した91歳の男性が駅構内の線路に立ち入り列車に衝突して死亡した事故に関し、鉄道会社(JR東海)から男性の長男、妻(当時85歳)に対する損害賠償請求事件で、長男の責任を認めず、妻の責任を認めた原判決に当事者双方が上告等を申し立てたものでした。
最高裁の結論は全員一致でいずれの責任も認めませんでしたが、理由は3対1対1に分かれました。
大橋元裁判官は「実際に行われていた介護は記録を見るだけで涙が出るほど手厚いもので、請求棄却という結論は早期に出た。他の裁判官も同様だったと思います」といいます。その上で、責任を免除することに消極的な従来の解釈をどこまで変更するか、その法律構成が問題になったわけです。従来の民法714条の解釈では免責要件は厳しいものだったからです。
多数意見は、妻・長男ともに「監督義務者」にも「準監督義務者」に該当しないという構成を取りました。これに対して岡部喜代子裁判官と大谷剛彦裁判官の「意見」は、「準監督義務者には該当するが免責する」と解釈するものでした。なお大谷裁判官は成年後見人は原則として法的の監督義務者に該当するとし、岡部裁判官は責任主体性は個別具体的な判断によると意見を述べています。
ちなみに「反対意見」は多数意見と意見が異なるもの、「意見」は結論は同じだけど理由付けが異なるもの、「補足意見(補足的意見)」は結論・理由は同じだけど付加的に述べるもの。
大橋弁護士は「考えが異なれば、反対意見や意見を書くのは当然として、問題は、補足意見を書くべきか、書かざるべきか。そこが各裁判官の判断になってくる」と言います。
その上で、補足意見には①批判・反論型、②敷衍・説明型、③言訳型、④叱責型(自分の出身に対するものが多い)、⑤運用指針・手続提示型、⑥解説・補完型があると分析して、詳細に具体例に基づいて解説して頂きました。
最高裁での審議の実情とは
年間事件数は、民事・行政が約8000件、刑事が約4000件、合計1万2000件に達します。
その中で訴訟事件は、民事・行政が約3000から4000件、刑事が2000件、合計5000から6000件になります。小法廷が3つありますから、各小法廷は3分の1の件数が継続していることになります。
最高裁は専門部制をとっていないので、すべての裁判官があらゆる種類の事件を取り扱います。そして事件の割り当ては機械的に行われます。なお5人の裁判官のうちの一人が主任になり、事件は主任に配転され、主任が裁判長になります。
小法廷の審議のやり方には2つあり、一つは「持ち回り審議」、一つは「正式審議(審議室審議)」が行われています。
いわゆる門前払いする案件は前者で処理されます。ちなみに第三小法廷は昔からメモを頻繁に書く伝統があるとのことです。調査官意見以外に主任裁判官のメモがついて訴訟記録とともに他の裁判官に回されるわけです。中には「こんな事件かわいそうだよね、弁護士何やってるんだ」という感想メモがついているだけということもあれば、法的なコメントを付けることもあるということでした。
なお持ち回り審議の途中であっても一人の裁判官からでも審議したいという意見がでれば、正式審議に移行します。
正式審議は評議室に5人の裁判官が集まって審議するわけです。第三小法廷は、原則火曜10時30分から正式審議を行い、場合によっては金曜にも開催します。毎週開催とは限らないそうです。調査官の報告書とは別に、主任裁判官の作成した審議メモも作成し事前に配布されます。それについて別の裁判官に意見があれば、別の審議メモも作成されて配付されます。
大橋弁護士の合議についてのイメージは二つあるとのこと。
つまり、どちらの説が正しいのかの決着をつける「戦いの場」という人もいれば、説の違いが何に由来するかを確かめる「違いを確認する場」という人もいます。
亡くなられた田原裁判官は前者の考え方に近い考えでした。大橋裁判官は後者の考えということでした。後者の考えでいると、どうして考え方の違いがでてくるのか好奇心が出てくると指摘しました。
ぎりぎりまで詰めても違いが分からなければ少数意見を書けばよいのであって、最高裁での議論は楽しいものだったということです。
最高裁調査官の実情と役割
最高裁調査官は主席以下41名います(全員裁判官)。調査官と裁判官の関係は事件ごとに決まります(ちなみにアメリカでは裁判官に専属します)。
調査官の役割は3つあり、「調査報告書の作成」、「裁判官の審議に陪席すること」、「判例解説の作成」です。
典型的な調査報告書は、事案の説明、争点、1審判決と原審、上告の趣旨、論旨の検討、処理方針という構成をとります。必要な文献・判例も添付され、数十ページになるものもあれば、2~3枚のこともあります。
難しい事件の場合は調査官室で研究会を開いて複数の調査官で検討することもあるとのこと。調査官室の不文律として、「事件について質問を受けたらいつでも応対すること」というものがあり、調査官室では非常に活発な議論が行われているそうです。
ちなみに最高裁判所裁判官が赴任して最初に最高裁に行くと、まず「裁判官は調査官室には来ないでください」と言い渡されるとのこと(会場笑いに包まれる)。裁判官が調査官室に来るとお相手しないといけなくなるし、即座には事件を思い出せないので、「必要であればすぐに裁判官室にうかがいますからいつでも呼んで下さい」と伝えるそうです。
現在はどの小法廷においても、審議には調査官が陪席することが原則とされていますが、陪席している調査官は裁判官の指示がなければ発言はしません。ただし議論が錯綜している時、「報告書を書いた君はどう整理する」と尋ねて発言を求めて参考にすることはあるといいます。
法廷意見の起案は主任裁判官が作成します(仮に反対意見であっても)。そのため、「〇〇判決」と裁判長の名の付けられた著名判決であっても、実はその裁判長が論旨に反対ということもあります。
調査官制度に対しては周知の通り、昔から批判もあるところです。これに対して、大橋弁護士は、「調査官意見が裁判官の議論に一切の影響を及ぼさないということはないですが、裁判官の審議の結果であることは間違いありません。特に第三小法廷では主任裁判官が自ら考えてメモを作成していますから」といいます。
そして「調査報告書」としては、オーソドックスなものが望ましい、つまり現在の判例・通説からしてどのような結論になるか、それに対してどのような批判があるかとまとめたものが良いということでした。
上告申立てと上告受理申立て
平成10年の民訴法改正によって上告申立て(民訴法312条)と上告受理申立て(民訴法318条)が区別され、それぞれの事由が別立てされています。
つまり上告理由は「憲法の解釈の誤り」、「その他憲法の違反」(312条)と同2項に列挙された6個の事由です。
一方、上告受理の申立事由は「最高裁判所の判例と相反する判断」、「その他の法令の解釈に関する重要な事項」(318条1項))です。
従って、本来は別の理由になるはずですが、最高裁に継続する訴訟事件の37パーセント前後が並行申立てになっており、しかも大半が同じ理由になっているということです。
並行申立の場合であっても、各要件該当性を個別に検討している書面を見ると、「代理人はよくわかっているな」という感想を持つということです。
並行申立が例外的に意味をもったある医療過誤事件
大橋弁護士は、「並行申立てはやめてほしい」と強調しますが、例外的に(逆説的に?)意味があった事案もあったということです。それはある医療過誤訴訟の事案です。
適切な医療を受ける期待権が争点になっていた最三小判28年7月19日判決です。ちなみに「判例秘書」には登載されていますが、各判例集には登載されておらず、大橋弁護士は「裁判所としてもあまり表に出したくない判決なんだと思う」ということです(追記:その後、判例時報2342号(平成29年10月21日号)「最高裁民事破棄判決等の実情(上)」7頁から10頁に解説が掲載されました)。
事案は、松果体腫瘍摘出術を受けた患者(被上告人)が、手術後に脳内出血が生じ、脳の器質的損傷のため高次脳機能障害等の後遺症が残ったケースについて、医療機関(上告人)に対して、医師は本件手術後に出血の徴候が出現した時点で患者の頭部CT検査を実施すべき注意義務があるのにこれを怠ったため、後遺症が残った、仮に上記注意義務違反と後遺症の残存との間の因果関係が証明されないとしても、後遺症が残らなかった相当程度の可能性を侵害されたと主張して使用者責任に基づく損害賠償を求めたもの。
原審は、医師の注意義務違反と因果関係を認めなかったものの、「C医師が上記注意義務を尽くさなかったことにより適切な医療を受けるべき利益を侵害され、これにより精神的苦痛を受けていることが認められるから、上告人に同苦痛を慰謝すべき責任を負担させることが相当である」として1100万円の支払を命じる限度で認容していました(以上は判例秘書より引用)。
周知の通り、最高裁は医療過誤分野において、義務違反と結果との因果関係が高度の蓋然性をもって立証できないケースについて、「相当程度の可能性」侵害に基づく慰謝料を認容しています。ところが原審は、重大な後遺症が残らなかった相当程度の可能性を侵害されたという最高裁の従来の枠組みで判断を示したものではなかったのです。
これに対して病院が上告申立てと上告受理申立てをしました。上告受理申立てが「原審の判例違反」を理由としていれば問題なく上告受理して破棄できました。ところが病院(上告人)の代理人弁護士が上告受理の理由に上げていなかったため、裁判所が上告受理した上での処理ができなかったというわけです。
しかし、「最高裁からすると、原審が明らかに間違っている。そして訴訟の経緯をみても、匿名協力医作成の意見書をそのまま利用してしまうなど最高裁としてもほっておくことができなかった。そこで上告について理由はなかったものの、職権で判断して破棄した」ということでした。
ちなみに最二小判平23・2・25集民236号183頁は、「患者が適切な医療行為を受けることができなかった場合に、医師が患者に対して、適切な医療行為を受ける期待権の侵害のみを理由とする不法行為責任を負うことがあるか否かは、当該医療行為が著しく不適切なものである事案について検討し得るにとどまるべきものである」(結論は否定)と判示していました。
これに対して本件最高裁は、平成23年2月25日判決を前提にした上、「主治医の医療行為が著しく不適切なものであったといえないから、不法行為責任の有無を検討しるような事案ではない、と判断したものになります。
大橋弁護士は「こんな理由で勝っても(病院の)弁護士は嬉しくないんじゃいか」と会場の笑いを誘いつつ、「基本的には並行申立てはやめて欲しいと思います」、そして「上告申立てをするために無理な憲法違反を主張していることがある(売買契約に基づく所有権移転登記を求めた事案で売買契約が認められなかったために敗訴した事案で、憲法29条の財産権侵害を主張するなど)。依頼者との関係でいろいろあることは弁護士として分かりますがが、やはり無理な申し立てはやめるべきでしょう」と強調しました。
弁護士が最高裁に提出する書面の目的とは~事案に応じた適切なキーワード
そして大橋弁護士は弁護士の書くべき書面について以下のようにコメントしていきました。
上告や上告受理申立には、「重要」など各要件が付されている。それを満たさないと裁判所は受理をしません。この点が、良い書面を考える上で重要になるといいます。
弁護士は「原審が間違っているんだから、最高裁がひっくり返してくれるはず」と思いがちであるが、重要・重大であることを意識しなければならない。事実誤認、量刑不当だけを訴えても裁判官の心をとらえる書面にはならず、最高裁で取り上げようとは思わない。
特に控訴理由書や控訴趣意書を引き写して提出するだけの書面があるが、これが最悪の書面になる。
誤解を恐れずにいえば、「法令違反」や「事実誤認」について数十頁もかけなければ論証できないのであれば、それは「重大」でも「著しく」もない。
少なくとも現在提出されている書面は長すぎるという認識では最高裁裁判官は一致している。弁護士側としては、最高裁の裁判官は記録を読んでいないのでは・・という不安があるんだと思う。しかし調査官は全記録を読む。裁判官も原判決は読んで一定の印象を持ちながら、上告理由書ないし上告申立書を読む。
弁護士が最高裁に提出する書面は裁判官のセンサーにさえひっかかれば良い。つまり、「もう少し調べないといけないな」「原判決を維持するにはちょっとおかしいな」と裁判官が書面を読むことで感じてもらえば良いのである。
他の元最高裁裁判官も様々な論考において「最高裁に提出する書面は長ければよいのではない」と指摘しているのは、そういう点にあるんだと思う。
そして、最高裁の裁判官に読ませて動かす文書としては、「短い文章の中にどうキーワードを盛り付けていくか。事案に応じた適切なキーワードを見つけられるかが勝負。事件の性格付けを表現するための言葉が必要なんだと思います」と締めくくりました。
3時間にわたる長い講演でしたが、最後には会場から積極的な質疑応答も行われました。
若い弁護士からは、「最高裁の国民審査についてはどのように感じていましたか?前から一度、直接聞いてみたかったんです」と場を和ませる質問も出ました。
ちなみに大橋元裁判官は「私はあんまり気にしていませんでしたが・・・順番を気にしている裁判官も確かにいましたよ」と回答し会場は和やかな笑いに包まれました。
◆ 参考文献
才口千晴「インタビュー」(LIVRA2008年12月号)
藤田宙靖「裁判官と学者の間で」(青山法務研究論集3号115頁・2011)
藤田宙靖「最高裁回想録ー学者判事の7年半」(有斐閣・2012)
藤田宙靖「憲法裁判所における調査官の役割(インタビュー)」(北法66巻2号83頁・2015)
宮川光治「インタビュー」(LIVRA12巻6号20頁・2012)
宮川光治「時代の中の最高裁判所」(自由と正義64巻6号20頁・2013)
田原睦夫「最高裁生活を振り返って」(金融法務事情1978号6頁・2013)
須藤正彦「インタビュー」(LIVRA2013年4月号)
鬼丸かおる「鬼丸かおる最高裁判事に聴く」(日本女性法律家協会会報52号60頁・2014)
岡部喜代子「岡部喜代子最高裁判事に聴く」(日本女性法律家協会会報54号54頁・2016)
「一歩前へ出る司法 泉徳治元最高裁判示に聞く」(日本評論社)
山浦善樹「前最高裁判事に訊く」(LIVRA2016年12月号)
投稿者プロフィール