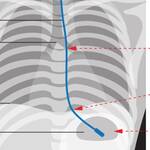裁判官が語る医療訴訟実務のバイタルポイントとは
目次
医療訴訟実務のバイタルポイント
ジュリスト(有斐閣)で「訴訟実務のバイタルポイント」というコーナーが開始しています(1501号から)。
第2回目の連載として専門訴訟として医療訴訟が取り上げられ、1510号(2017年9月)で前編、1511号(2017年10月)で後編が取り上げられています。
門口正人前名古屋高裁長官が司会をして、東京地裁医療集中部(民事14部)の手嶋あさみ部総括判事と東京地裁9部の渡部勇次部総括判事が対談形式で医療訴訟を取り上げたもの。
興味深く読ませてもらいましたので少し取り上げてみたいと思います。
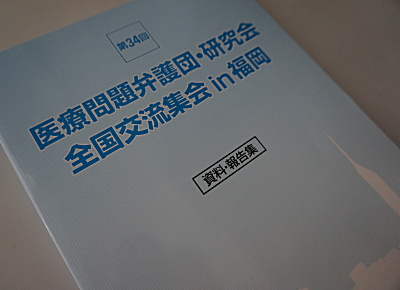
二極化する患者側弁護士の能力
最近、九州のある県の医療機関側弁護士と雑談する機会がありました。
そのとき、そのA弁護士は「最近は医療機関側が勝ちやすいというか、仕事をしやすいというか・・率直に言うと問題のある患者側弁護士が増えている」とコメントしました。
私が弁護士になった20数年前は、医療過誤事件というとその専門性から取り扱う弁護士は極めて限られていました。必ずといって良いほど患者側弁護士の研究会や弁護団に所属した上、まずは先輩弁護士とともに活動してノウハウを学んでいきました。
私も弁護士登録とともに、九州山口医療問題研究会に所属して先輩弁護士とともに医療調査を行ったり、医療過誤訴訟を弁護士2~3名の弁護団体勢で遂行しつつ、医療過誤の実務を学んできたものです。
私は弁護士1年目からカルテの証拠保全を数件経験したほか、訴訟提起も数件行うことができました。
今でも初めて証拠保全に赴いた医療機関(個人の産科でした)の対応は覚えています(裁判官とともにチャイムを鳴らすのですが、お爺さん院長はなかなか出てこず、ようやく提出されたカルテには走り書きしたような跡が多数見受けられました)。また最初に主任として手がけた裁判は良い解決に終わり、そのご家族とは今も交流しています。
いずれにしろ先輩弁護士との実務経験は大きな財産になって今につながっているのです。
ところが司法制度改革後、弁護士増員したことによって、いわゆる研究会や弁護団に所属せず、また先輩弁護士とともに実務を行って学ぶこともせずに、交通事故の感覚でいきなり医療過誤を受任する弁護士が少なからず出てきているのです。
ジュリストの座談会でも以下のように端的に言及されています
門口 専門性という点で、最近の弁護士の能力とか経験について、どのように思われますか。
手嶋 二極化とまでは申しませんが、医療訴訟についての経験が豊富で、必要な知識、ノウハウを蓄積された方と、新しくこの類いの訴訟を扱われるようになった方とで、相当程度力量の差というのはあるように思います。
門口 当事者側が専門性に劣るということから、ご苦労もあるのでしょうか。
手嶋 正直いいまして、その点を感ずる代理人もいます。苦労している事件もあります・・・最近、医療訴訟の経験の少ない訴訟代理人の関与も増加してきていることから、訴訟提起前の準備が非常に重要であって、そこが不十分と考えられる事案もあるということで、かなりの期待を込めて、お願いしたいことをまとめました(ジュリスト1510号69頁)
手嶋 医療訴訟の経験が長い代理人、例えば医療問題弁護団に属して長く活動されている代理人のような方ほど、提訴前の準備を極めて緻密にやっておられるという印象です。事実関係を基本的な資料であるカルテ等から読み解く、関連する基本的な医学文献に当たる、そして、事案に即した協力医を見つけーこれは大変な努力をしておられるのだと思いますがー、具体的事案に当てはめた形での医学的知見を求め、訴訟における主張立証の見通しについて、法的な吟味も含め、緻密に検討しておられることがうかがわれます(ジュリスト1511号60頁)。
医療調査、そして患者・遺族への説明の重要性
患者側で医療過誤を専門的に扱う弁護士は、原則として「医療調査」から受任します(例外的に医療機関側が過失を認めている場合や既に損害額の提示があっている場合は、例外的に損害賠償請求(示談交渉)を受任します)。
「医療調査」というと、患者側弁護士からすると当然の作業なのですが、実は患者・家族含めて一般の方からすると理解して頂くのが難しい業務という側面もあります。
弁護士に相談するわけですから、納得できない治療にあった、予期せぬ重大な結果が出た、場合によっては家族が死亡したというケースがほとんどです。
患者・家族からすると、「重大な結果」ないし「説明を受けていない(もしくは説明を覚えていない)予期せぬ結果」=医療機関の責任、つまり医療過誤であると考えておられる方が大半だからです。
その方々に医療過誤の構造を丁寧に説明して、医療調査の意義を理解して頂く必要があります。
「医療調査」は診療録に基づいて事案を把握し、医学文献・論文を検討して、第三者の協力医にも話を聞く等しながら、医療機関の診断・治療に法的責任がうかがえるかを検討してくものです。
医療調査の結果、もちろん損害賠償請求に移行していくべき事案もありますが、損害賠償請求が困難であることが判明する事案も少なくありません。
医療調査はその意味で患者・家族が医療・治療の内容を理解して納得いく過程でもあるのです。ところが、どうしても責任追及したい、責任追及できないのであれば費用をかけて医療調査なんかしなかったと言い出される方も出てきます。
私は福岡県弁護士会の副会長を経験したので弁護士会に対する弁護士の苦情を受け付ける業務もしています。その苦情の中で、「医療過誤を依頼したら、弁護士から裁判しても勝てないと言われて、費用も返してくれない」という苦情も散見します。おそらくは医療調査の結果、損害賠償請求は困難という説明をしたものであり弁護士の業務としては問題ないと思われますが、そもそも医療調査とはどのようなスキームなのかの説明が不十分だったから苦情に発展してしまったものと推察します。
ですから受任時点できっちりと過失や因果関係の判断枠組みや医療調査の趣旨をご説明するのはもちろん、途中の打合せの段階でも繰り返しご説明し、最後に結果を共有してもらう・理解してもらうことも患者側弁護士としての重要なスキルといえるのです。
この重要な依頼者への説明という側面についてジュリスト座談会でも触れていました。
門口 依頼者との関係について、何か気になる点はありますか。
手嶋 医療訴訟の患者側ご本人は、生じてしまった重大な結果に対する無念さや、それがなぜ生じたのかという疑念、医療機関に対する不信感、適切な医療を受けられなかったという切実な思いを抱えて訴訟に至っています。
そうであるからこそ、裁判になったときにどういう枠組みで判断されることになるのかを、提訴に当たり、患者側代理人がきちっと当事者に説明されているのだろうかという思いを持つことはあります。法的な注意義務違反があり、それと結果との間の因果関係が認められて初めて損害賠償が認められることになるわけで、それに至らない場合には、必ずしも最善の医療行為が行われたのではないとしても、法的には救済は得られない。
ある意味での裁判の限界ということかもいれませんけれども、そのような基本的な仕組みや法的見地からの見通し等について、法律専門家としてきちっと説明をして、当事者本人との間で認識を共有しておくことは、訴訟を進めていく上でも、より良い解決を図る上でも重要なことだと思います・・・手嶋 ・・・訴訟提起前の調査活動が、訴訟まで至らずに早期に時間を解決する上でも重要ですし、訴訟になってからも極めて重要であるという認識が前提としてあります(ジュリスト1510号69頁)。
医療過誤訴訟の医療現場への影響
座談会の最後では医療現場への影響、そして最近の空気の変化についても触れています。
裁判まで至らない医療事故・医療過誤事件においては、様々な医療機関による様々な対応に接していますから一部異論もあるのですが、その是非はともかく、裁判官の意識の一つとして紹介しておきたいと思います。
門口 いよいよ時間が押し迫ってまいりましたので、最後にまとめの意味で幾つかお伺いします。医療訴訟について世間の関心を集めたときに、医療界から、司法自体が医療を萎縮させているのではないかという批判がありました・・具体の裁判でどのようにお応えしているか、お話しいただくことはできますか。
手嶋 大野病院事件について少し触れましたが、産科医療に関する議論はその一つの典型であったように思います。産科医療の分野では、とりわけ分娩時の医療事故について過失の有無の判断が困難な場合が多く、裁判で争われるケースも少なくなかったことから、このような紛争の多さが、産科医不足の理由の一つであると指摘されました。この問題については、直接的には、産科医療補償制度の創設という形で解決が図られました・・・このような議論やその過程を通じて、医療事故というものを受け止める社会的な意識も、医療機関側の意識や姿勢も大きく変わってきたのではないかということです。
かつては、医師には間違いがあってはならないということが前提とされていたように思います。
それが、今はヒューマンエラーを前提として、それをいかに防ぐか、起こったときにどう対処するのかという方向に、大きく考え方が変わってきているように思えます(ジュリスト1511号71頁)。
投稿者プロフィール