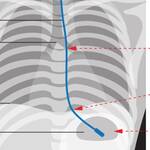子宮頸がんワクチン訴訟の弁護士意見陳述、過去の薬害訴訟の経験に学ぶ
目次
子宮頸がんワクチン薬害訴訟
子宮頸がんワクチン薬害訴訟の福岡地裁第4回期日が平成29年6月14日に行われました。
現在、福岡、東京、大阪、名古屋と4地裁で口頭弁論が開かれており、原告、被告らがそれぞれ準備書面を提出して主張を行っている段階です。
福岡地裁では毎回、原告本人による様々なワクチン接種後の被害を意見陳述するとともに、弁護団による意見陳述を行っています。
この意見陳述とは提出した準備書面に関連して主張を口頭で補足するものという取り扱いです。意見陳述の書面自体は証拠にはならず、裁判所の記録では雑記録として綴じられます(原告本人の意見陳述は、尋問前に整理・加筆して陳述書として改めて証拠提出します)。
とはいえ毎回の長大な準備書面では分かりにくい主張内容に触れつつ、裁判所の心証に訴えるという意義があるものです。
今回は原告弁護団から徳田靖之弁護士が意見陳述を行いました。
過去の集団訴訟を紐解きながら今回の子宮頸がんワクチンの問題に触れる含蓄のある意見陳述でしたので、若干の解説をふまえてご紹介したいと思います。
1 はじめに
私は、司法修習は21期、来年で弁護士生活50年目を迎えます。この間、この九州の地において、水俣病裁判、薬害スモン訴訟、じん肺訴訟、薬害AIDS訴訟、薬害肝炎訴訟、B型肝炎訴訟等に直接・間接に関与してきました。
その経験から、本件訴訟における主要争点である、因果関係ないし発生機序の解明のあり方、薬害において当該薬剤の効用論が果たした役割について意見を申し述べることとします。
初めて徳田弁護士にお会いしたのは1993年、私が司法修習生の頃でした。当時、薬害エイズ訴訟が佳境を迎えつつあり、修習の合間に東京弁護団会議に参加させてもらったり、東京地裁の弁論を傍聴していました。
東京地裁の弁論後の報告集会の際、薬害エイズ東京弁護団の事務局長だった鈴木利広弁護士(後の薬害肝炎全国弁護団代表)から紹介して頂きました。
その後1995年に弁護士登録してからすぐ、薬害エイズ九州弁護団で一緒に仕事をさせて頂き、ハンセン病違憲国賠訴訟でも八尋弁護士とともに共同代表を務めた徳田弁護士とともに弁護団活動を行いました。
その誠実な人柄、緻密な法的分析、リーダーシップは衆目の認めるところです。
2 原告らの病態とワクチン接種との間に因果関係が認められるべきこと
原告らが今回提出した準備書面(3)は、原告たちの病態とワクチン接種との間の因果関係について、複数の専門的な臨床医らによる調査研究の結果等を踏まえて明らかにしたものです。
先ほど意見陳述をした原告番号30さんのように、ワクチンを接種した少女たちには、極めて多様な症状が生じています。
このことは、これまで本法廷で意見陳述をしてきた少女たちを目の当たりにして、裁判所においても認識されていることかと思います。
このように、症状が多様であること、その故に、診断基準が確立していないということは、過去の薬害、公害など、健康被害が問題になった事件において、等しく認められてきたことです。しかし、そのことは、訴訟における発生機序や因果関係の解明において、何ら障害になることはありませんでした。
過去の薬害、公害等における、因果関係の解明は、以下に述べる通り、こうした多様で非特異的な症状を呈する被害事実に、正面から取り組んだ、臨床医らによってなされてきたのです。
徳田弁護士が指摘するように、過去の薬害においても、診断基準が確立されていないために因果関係が激しく争われてきました。
特に水俣、スモン、そして子宮頸がんワクチンのように、医学的知見が確立することを待たず、いわば医学的知見の進展と並行的にスタートした集団訴訟の場合には特に大きな争点になってきます。
この点、薬害C型肝炎訴訟は、1964年に承認され1994年頃まで使用された止血剤(血液凝固因子製剤)によるC型肝炎被害について、2002年に集団訴訟を提起しました。
1987年から88年にかけて集団感染が大きくメディアでも報道されたものの、1989年に薬害エイズ訴訟が開始したばかりだったこともあり、当時提訴までには至らなかったのです。
そのため止血剤によるC型肝炎感染問題は、「薬害エイズの残された課題」とも言われており、1996年に薬害エイズが和解によって一定の解決を経た後、検討を経て訴訟に至ったものでした。
このように薬害C型肝炎訴訟が2002年にスタートした時点では、新たな被害者が発生しているものではありませんでした(もちろん被害者であることを知らないままC型肝炎に苦しんだり、感染の告知さえ受けずに症状・肝炎のステージを悪化させてしまうという被害は継続していました)。
ですから集団訴訟を提訴した2002年時点では、C型肝炎の医学的知見も進み、過去の行政の問題点についてある程度冷静に分析できるようになっていました(とはいえ国は責任を否定し、加害企業も最後まで責任を争うわけですが)。
これに対して、子宮頸がんワクチンのようにまさに医学的知見の集積中である課題の裁判は、特有の難しさがある一方、訴訟を起こすことによって、結果的に新たな被害者を発生させないという役割も果たしているともいえるでしょう。
3 因果関係、発生機序の解明における基本的視点について
⑴ 因果関係、発生機序の解明のあり方という論点で、私がまず思い出すのは、水俣病事件です。病像が多様であったことと並んで、因果関係(発生機序)の解明を阻んだのは、事件の発生が公表された当初の時期に、権威とされる東大あるいは東工大の教授らが、海中の未処理爆弾説や「有害水銀は、人体に吸引されない」等という「学説」を公表したことにありました。加害企業の利益を背景にした、こうした権威の「学説」に対して、当初の段階で、有機水銀原因説を明らかにしたのは、地元の熊本大学病理学教室の武内教授らの地道で実証的な研究でした。
⑵ 私が原告代理人として関与したスモン訴訟においても、その因果関係の解明において、その症状は、非特異的で、重松逸造医師によれば、「どこにでもある症状」で多様極まるものとされていました。
このため、当初は、診断基準どころか、病像自体もマチマチに把握され、集団的な発生が確認された地名毎に戸田病だとか、佐伯病だとか言われたりしました。
そのうえで、京大ウイルス研究所が公表した「ウイルス原因説」が、発生機序を解明するうえでの大きな障害となりました。加害企業たる田辺製薬が、このウイルス説に依拠して、その発生機序を徹底的に争ったことは、記憶に新しいところです。
結局、その原因が、整腸剤キノホルムであることを解明したのは、地方において、多数の被害者の治療に当たった研究者らのグループであり、その提言に基づいて、キノホルム製剤の販売を中止した所、一挙に新規患者の発生が激減して、論争が決着したのです
「症状が非特異的で、診断基準が確立していない」、「ワクチン未使用者に原告らと同様の症例報告がある」、「WHOが因果関係を認めていない」という被告企業らの主張は、まさにこうした過去の薬害・公害事件等において、加害企業が繰り返してきました。
徳田弁護士が指摘するように、子宮頸がんワクチン訴訟における被告企業の応訴態度や主張を見ると、過去の集団訴訟の訴訟経過がフラッシュバックするような感もするわけです。
4 薬害において、薬剤効用論の果たした役割について
⑴ 本件訴訟に参加して驚いたのは、被告企業によるHPVワクチンの効能に関する異常なまでの大合唱でした。
しかし、私が代理人として関与した、薬害AIDSの問題では、血友病患者に対するHIV感染の原因となった非加熱濃縮凝固因子製剤について、血友病専門医や製薬会社らは、既にアメリカで血友病患者にHIV感染が数例報告されていた時点において、この薬剤の販売が停止されることは、血友病患者を暗黒時代に逆戻りさせるとの大キャンペーンを展開して、その販売停止に抵抗したのです。
その結果が、日本の血友病患者5、000名の内、1、850名がHIVに感染し、その半数以上がAIDSで死亡するという空前の薬害被害を生み出したのです。
⑵ また、薬害サリドマイド事件では、ドイツにおけるレンツ博士による警告を知りながら、小児や妊娠中の女性も使用できる「夢の睡眠薬」との効用論が、日本における販売停止を決定的に遅らせたのでした。
スモン事件においても、その原因究明を遅らせた要因の一つが、キノホルムを使用している整腸剤が、当時のわが国では、数十種類に及んでいるという、販売停止した場合の影響の大きさへの「考慮」でした。
(3) 薬害肝炎において、その原因となったのは、大量の出血などでDICをきたした症例に投与された止血剤としての「フィブリノーゲン製剤」でした。
東北地方において顕著だった、出産時の母体の死亡率を著しく改善させることに献身された弘前大学の品川信良名誉教授は、面談に訪れた私に対して、フィブリノーゲン製剤の使用を推奨した過去を振り返って、「効能にのみ目を奪われて、副作用の深刻さに思いが及ばなかった」と述懐されました。
(4) 私は、本件訴訟における被告企業の応訴態度に最も欠けているのは、こうした過去の薬害事件の教訓に学ぶということではないかと思うのです。
徳田弁護士はこのように被告企業らの過去の薬害事件の教訓に学ぶ姿勢のないことを厳しく指摘しつつ、最後に薬事法の緊急命令の意義について言及します。
5 薬事法の緊急命令の意義と本件訴訟
本件では、国が、HPVワクチンについて、定期接種化から約2か月後に「積極勧奨の中止」を行っています。
私は、この点に関して、スモン事件の解決後に改定された薬事法の「緊急命令」の意義について述べておきたいと思います。
スモン訴訟は、推定被害者2万人、提訴原告7、000人という我が国最大の薬害事件でした。その深刻且つ甚大な被害を教訓に設定されたのが、薬事法の緊急命令です。
その立法趣旨を厚生省(当時)の薬務局は、「薬害の防止のためには、薬害の発生が相当程度予想されるに至った時点で、科学的因果関係が確定されるまでの間、当該薬剤の販売を中止することが必要不可欠だ」と説明しています。
危険なHPVワクチンを認可し、緊急促進事業、さらに定期接種化によってその普及を図った国の責任は免れません。しかし、定期接種化後約2か月後の「積極勧奨の中止」措置についてみるならば、それは、この緊急命令の考え方にそうものであり、世界有数の薬害大国としての我が国が幾多の痛ましい犠牲の上で到達した対応であって、世界に例がないことは、むしろ誇るべきものだと私には思えます。
最後に、本件訴訟の審理が我が国における過去の薬害・公害事件の痛ましい教訓を正しく踏まえた形で進められることを切に願って、私の意見陳述といたします。
子宮頸がんワクチンについて、国は2013年6月に「積極勧奨の一時的な差し控え」を行い現在に至っていますが、企業らは早期の再開を目指した動きを止めていません。
医学的知見が集積するのを待たずに、そして既に発生した被害に対する補償がなされないにもかかわらず、仮に国が積極勧奨を再開するとすれば、それは新たな被害者を漫然かつ積極的に生み出すものに他ならず、国は作為の加害責任を負うことになります。
訴訟においても国は、意見陳述は被告企業らに任せて、なるべく企業の陰に隠れるという姿勢を崩していません。訴訟による責任の明確化だけでなく、この定期接種の問題についても国が企業らの主張に流されて政策決定することのないように、注視していく必要があるといえますし、その点にまで踏み込んだ分かりやすい弁護士意見陳述だったと思います。
投稿者プロフィール